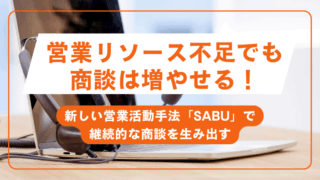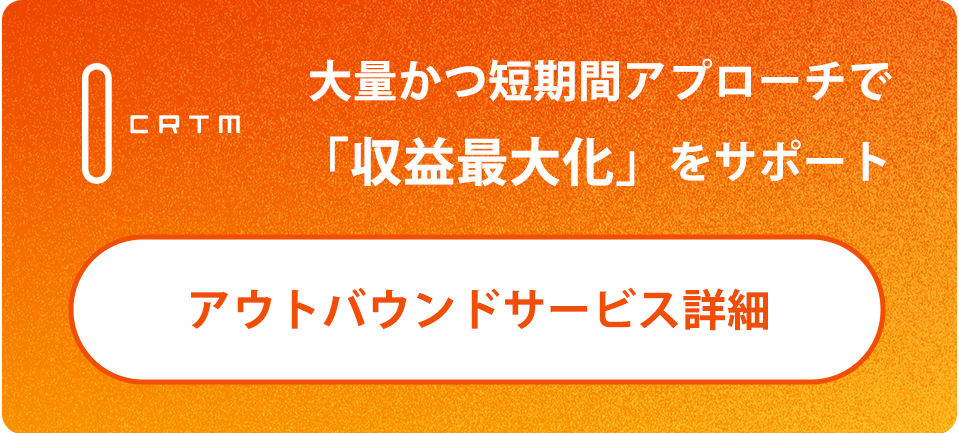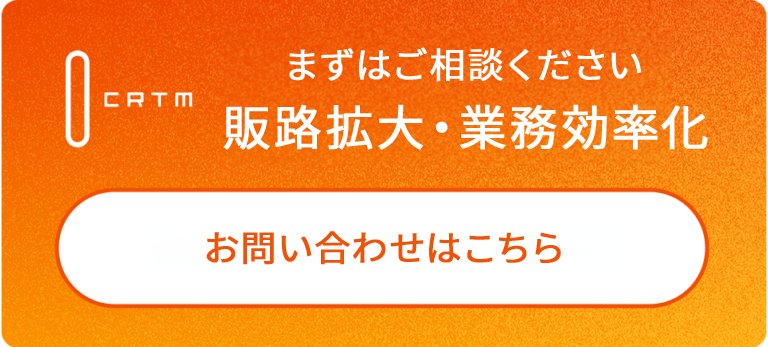営業代行を検討している企業の多くが直面するのが「費用感がつかめない」という課題です。以下のような悩みをお持ちではありませんか?
・成果報酬型と固定報酬型、どちらが自社に合うかわからない
・テレアポ代行や商談獲得型など、費用相場が業務ごとに異なる
・営業代行会社の見積もり内容に違いがあり、比較が難しい
本記事では、営業代行の料金相場や代表的な料金形態の違いをわかりやすく解説します。2025年時点の最新情報をもとに、自社に適したコスト感と選び方のポイントを整理。コストを抑えつつ、営業成果を最大化する外注戦略を検討したい企業担当者の方に役立つ内容です。
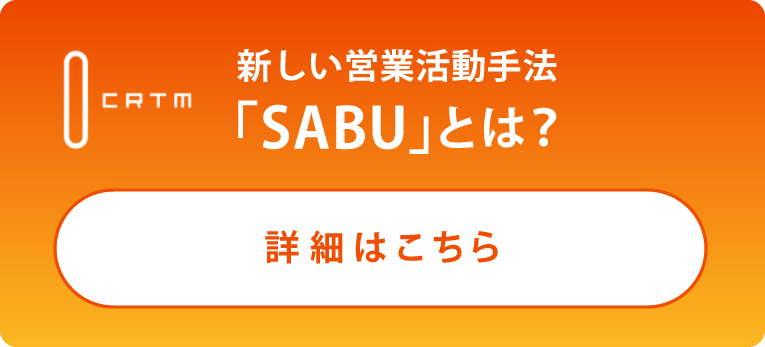
営業代行の料金はどう決まる?料金形態の相場

営業代行サービスの費用は、依頼する業務の範囲や成果目標、契約形態によって大きく異なります。まずは代表的な料金体系を理解しておくことが重要です。
主に以下の3つに分類されます。
・固定報酬型:毎月一定額を支払うモデル。安定した予算管理が可能。
・成果報酬型:アポイントや成約などの成果に応じて費用が発生する。費用対効果が明確。
・ハイブリッド型:固定+成果の組み合わせ。リスクとリターンのバランスを取りたい企業に適している。
どのモデルにもメリット・デメリットがあるため、自社の営業課題やリソース状況に応じて選択する必要があります。
固定報酬型と成果報酬型の違いとは
以下の表は、代表的な2つの料金形態の違いをまとめたものです。
| 項目 | 固定報酬型 | 成果報酬型 |
|---|---|---|
| 支払いタイミング | 毎月定額 | 成果が発生した都度 |
| コストコントロール性 | 高い(予算管理しやすい) | 変動性あり(成果数に応じて増減) |
| 初期費用・準備工数 | 比較的多い | 比較的少ない |
| リスク負担 | 企業側が大きめ | 代行会社側が大きめ |
| 適した企業規模・目的 | 中~大手企業/継続的な営業支援 | スタートアップ/短期で成果重視 |
固定報酬型はコストが読みやすい一方、成果が出ない場合も料金が発生します。
一方で、成果報酬型は費用対効果を重視した企業にとって魅力的ですが、成果基準が曖昧な場合はトラブルの原因にもなり得ます。
契約前には、「成果」の定義や評価指標を明確にすることが非常に重要です。
タイプ別で見る営業代行の費用相場
営業代行と一口に言っても、依頼する業務内容によって費用相場は大きく異なります。2025年現在、代表的な営業代行のタイプは次の3つです。
・テレアポ代行(アポイント獲得)
・商談代行・商談設定型(訪問・オンライン含む)
・契約獲得型・成約報酬型(クロージングまで実施)
ここでは、それぞれの代行タイプについて、料金目安と特徴を詳しく解説します。
テレアポ代行の費用目安と特徴
テレアポ代行は、新規顧客開拓の初期段階に活用されるケースが多く、最も依頼が多い代行業務です。費用は「1件あたりの架電数」または「アポ獲得件数」に応じて設定されることが一般的です。
・料金相場(2025年現在)
| プラン内容 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 架電単価型 | 1件あたり100~300円 | 架電数が多い場合は割引適用あり |
| アポ獲得型(成果報酬) | 1件あたり8,000円〜25,000円 | アポの質や商材の難易度により変動 |
| 月額固定型 | 月10万円〜30万円程度 | 架電件数の上限やレポート内容に応じて |
・特徴と注意点
・アプローチリストは自社提供か代行会社提供かで費用が異なる
・商材の単価が高いほどアポ単価も上がる傾向
・スクリプト作成やトーク品質によって成果が大きく変わる
・初期1ヶ月はテスト期間として設定する企業も多い
テレアポ代行は、リード獲得の入口として機能しますが、質の高いアポイント取得にはトーク精度とターゲットの明確化が不可欠です。
商談獲得型・契約獲得型の費用レンジと成果水準
テレアポでアポイントを取得した後、実際に商談や契約獲得までを担う営業代行も存在します。これは営業リソースが不足している企業や、スピード感ある営業活動を求める企業に選ばれています。
以下に、それぞれの業務タイプの費用相場と特徴を示します。
・費用相場(2025年現在)
| 項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 商談設定(訪問 or オンライン) | 1件あたり15,000〜50,000円 | 業界や商材の単価・難易度で変動 |
| 成約報酬型(受注単位) | 契約額の10〜30% | 高単価商材では報酬率が下がる場合あり |
| 月額固定型(商談+報告) | 月20万〜50万円前後 | レポートや同行内容によって変動 |
・主な特徴と活用ポイント
・クロージングまで任せる場合、営業代行側のスキルと業界理解が重要
・BtoB商材やITサービスなど、専門性の高い商談に強い代行会社も存在
・初期設定費やスクリプト構築費が別途発生するケースがある
・成約報酬型の場合、報酬の「成果定義」や「算出方法」についての事前合意が必須
商談や成約まで依頼する場合は、営業戦略にどこまで踏み込んでもらうかを明確にし、契約書の中で業務範囲をはっきりさせておくことが成功のポイントです。
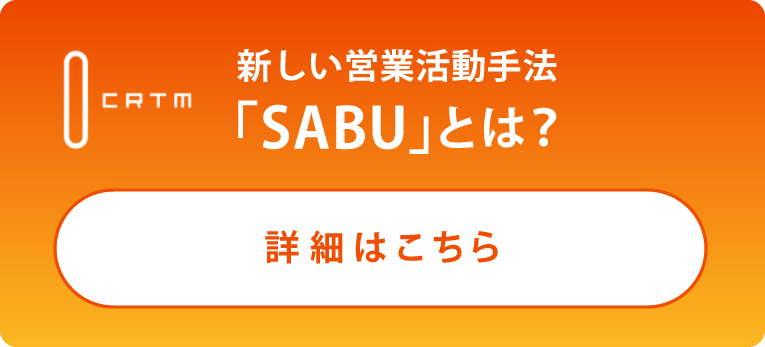
営業代行費用を左右する要因と見積もりに差が出る理由
営業代行サービスの費用は一見似ていても、実際の見積もりには大きな差が出ることがあります。その違いは、主に以下のような要因によって生じます。
費用に影響する主な要素一覧
費用の差を生む具体的な要素は以下のとおりです。
・商材の単価・難易度
┗ 高額商品や専門知識が必要なサービスはコストが上がりやすい
・ターゲットの属性・業界
┗ 経営者や大手法人をターゲットにする場合、アプローチが難しく単価が高くなる傾向
・アプローチ方法の種類
┗ テレアポ・メール・訪問など手法ごとにコストが異なる
・依頼範囲の広さ(リスト作成、スクリプト作成、レポート提出等)
┗ ワンストップで対応する会社ほど費用が高くなりやすい
・対応人員数・体制の有無
┗ 専任担当・複数人で対応するプロジェクトは料金が高めに設定される
・成果の定義やKPIの難易度
┗ アポだけでなく、成約や売上まで求めると単価が上昇する
これらの要素は各社の営業戦略や業務内容によって異なるため、見積もりを依頼する際には、具体的な要件や目的を明確に伝えることが不可欠です。
営業代行の費用対効果を高めるために意識すべきこと
営業代行は便利な反面、やみくもに依頼すると費用ばかりかかって成果につながらないケースもあります。ここでは、費用対効果を最大化するための実践的なポイントを紹介します。
無駄なコストを削減する3つの工夫
・自社の目的とターゲットを明確にする
┗ 何のために営業代行を導入するのか(アポ獲得、成約、売上向上など)を明確にし、依頼内容にブレが出ないようにする
・成果指標(KPI)の設定と共有
┗ アポイント数や成約数など、評価軸を数字で示し、代行会社とすり合わせることで無駄な工程を減らせる
・業務範囲・費用項目を細かく確認する
┗ スクリプト作成やリスト精査、レポート作成など、追加費用が発生しやすいポイントを事前に把握することで、予算オーバーを防止
また、営業代行会社と密に連携を取り、定期的なフィードバックや改善ミーティングを行うことでパフォーマンスは向上します。
費用対効果を高めるには、「依頼して終わり」ではなく、「一緒にPDCAを回す姿勢」が重要です。
営業代行の費用を抑えるために注意すべきポイント
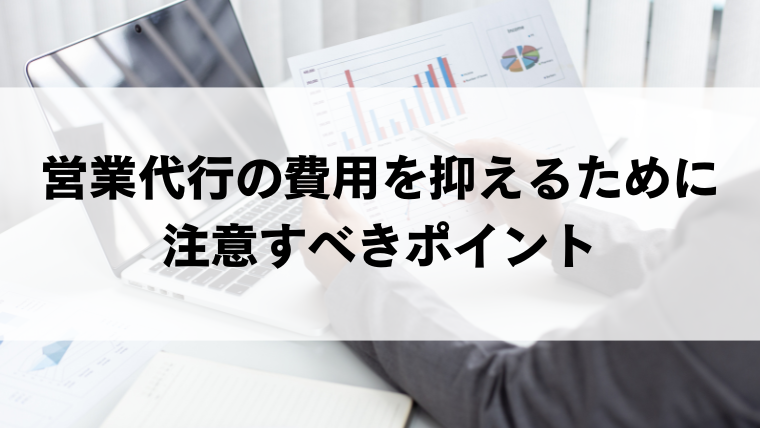
営業代行は、うまく活用すれば営業リソースの最適化や成果向上につながりますが、不用意な選定や運用によってコストが無駄になるケースもあります。ここでは、失敗しないための注意点を解説します。
無駄なコストを防ぐチェックポイント
・費用項目が曖昧なまま契約しない
┗ スクリプト作成や報告書提出などが「オプション扱い」で別料金になっている場合があるため、契約前に詳細を確認しましょう。
・成果の定義が不明確なまま依頼しない
┗ 「アポ件数」か「成約数」か、「質」か「量」かの基準が曖昧なままだとトラブルの原因になります。
・実績や得意業界の確認を怠らない
┗ 自社の業界・商材に合った知見を持っているかどうかで、成果の出やすさは大きく異なります。
・過度な成果を短期間に求めない
┗ 営業代行は魔法の杖ではありません。商材や業界によっては成果までに時間がかかることもあります。
これらの落とし穴を回避するには、自社の営業戦略と照らし合わせて、費用対効果が見込める体制で委託することが重要です。
まとめ
営業代行の費用相場は、サービス内容や料金形態(固定報酬型・成果報酬型など)によって大きく異なります。契約前には、成果の定義や支援内容、実績などをしっかり確認することが重要です。費用だけでなく、自社の営業戦略や目標との相性を考慮し、信頼できる営業代行会社を選定することが成功への近道となります。まずは複数社から見積もりを取り、比較検討を進めましょう。
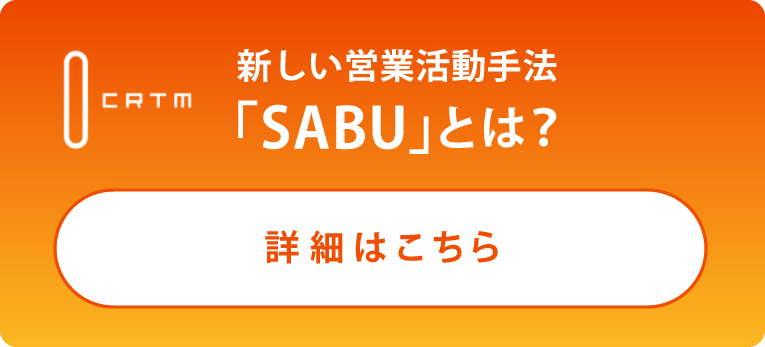




とは?選び方・活用法・CRMとの違いを徹底解説-2-640x360.png)