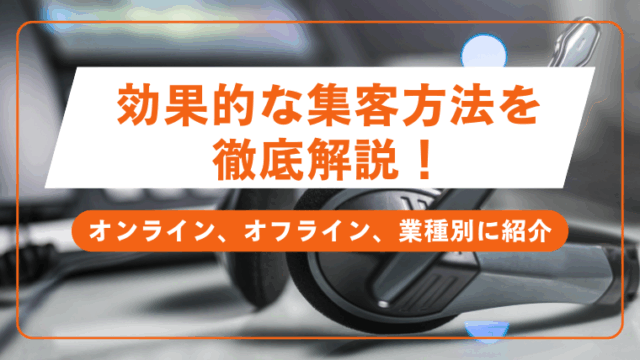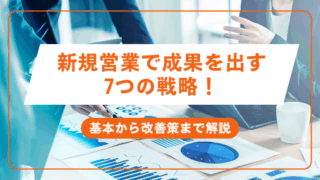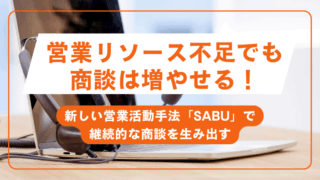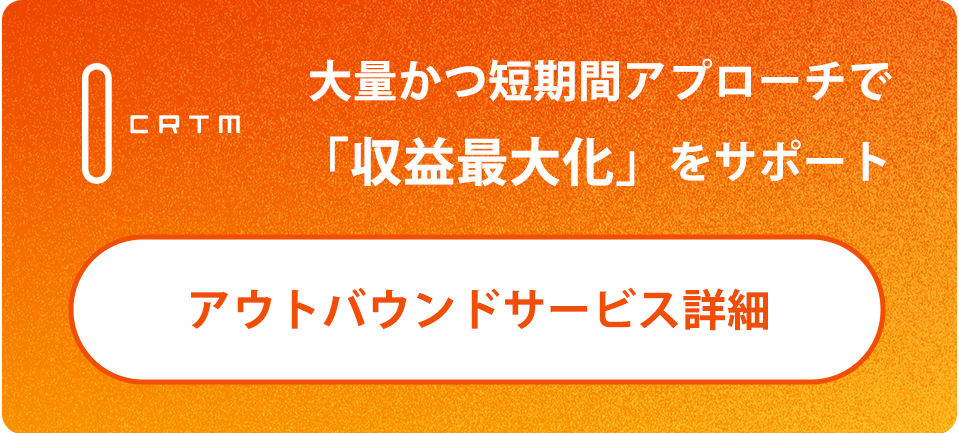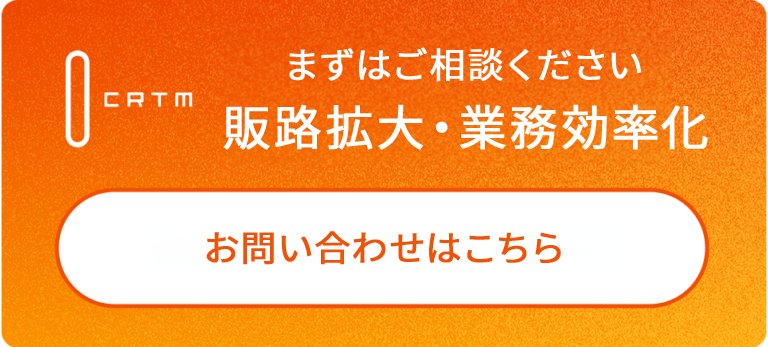新規顧客の獲得は、多くの企業にとって永続的な課題です。
市場や顧客ニーズが多様化するなかで、従来の集客手法では思うような成果が得られず、「何から手を付けるべきか分からない」と感じている企業も少なくありません。
本記事では、オンライン・オフラインを問わず効果的な新規集客の方法と戦略を体系的に解説。
具体的な施策例や、チャネル選定の考え方、成果を上げるためのデータ活用のポイントまでを、実践視点でわかりやすく紹介します。
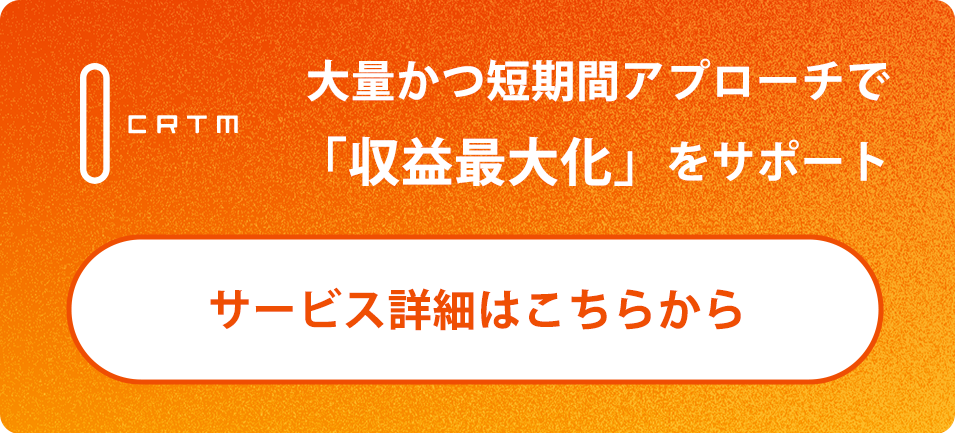
新規集客がうまくいかない企業が増えている背景
既存顧客への依存が限界を迎えている
多くの企業が売上の大半を既存顧客に頼っており、「新規顧客の獲得」は後回しにされがちです。
しかし市場が変化し続ける今、既存顧客だけに依存する営業体制はリスクが高まっています。
特に、紹介頼み・反響待ちなど受け身のスタイルでは、競合に先を越される可能性が大きくなります。
新たな市場や見込み顧客層に積極的にリーチする仕組みが必要です。
戦略不在の“施策先行”が成果を阻害する
Web広告、SNS運用、SEO対策…こうした施策に取り組んでいても、「誰に何を届けるのか」という戦略設計が欠けていれば、集客の質は上がりません。
短期の成果を求めて施策を増やすほど、「目的の見えない施策疲れ」に陥りやすくなります。
特にBtoB領域では、ペルソナ設計・カスタマージャーニー設計を軽視した施策が失敗の原因になりがちです。
デジタルとリアルの使い分けができていない
オンライン集客が主流となる一方で、業界やフェーズによってはリアルチャネルの方が有効な場面もあります。
しかし多くの企業では、「オンラインで何となく集める」か「オフラインに偏る」かのどちらかに偏りがちです。
本来は、顧客接点ごとに最適なチャネルを設計し、双方を連携させることで、集客の幅も精度も高まります。
新規集客の全体像と戦略設計について

新規集客は単なる「施策の実行」ではなく、設計→実行→検証→改善という一連の戦略的プロセスで初めて成果につながります。
また、オンライン・オフライン問わず、「誰に」「どんな価値を」「どう届けるか」という視点が欠かせません。
ここでは、集客の全体像を整理しつつ、戦略設計のベースとなる考え方を解説します。
新規集客における3つのステップ
新規集客は大きく以下の3ステップで構成されます。
- 認知獲得(まず知ってもらう)
- 興味・関心喚起(課題意識を持たせる)
- 行動促進(コンバージョン)(問い合わせ・資料請求・来店など)
この流れを意識することで、「どのチャネルを、どの目的で活用するか」が明確になります。
ターゲットとチャネルの整合性がカギ
集客施策の良し悪しは、「誰に向けているか」と「どのチャネルを使うか」の整合性で大きく変わります。
- 若年層 → SNS広告や動画広告など、感覚的・視覚的訴求が強い手法
- BtoB決裁者 → リスティング広告・オウンドメディア・展示会など論理的判断軸が必要な手法
- 店舗型ビジネス → Googleビジネスプロフィールやチラシなど地域密着型が有効
ペルソナ・カスタマージャーニーをもとに、「チャネルの使い分け方」を前提にした戦略設計が重要です。
オンラインとオフラインを連携させた設計を
近年は「オンラインで集客して、リアルで商談・接客」という流れが主流になりつつあります。
しかし、多くの企業はチャネルごとに施策を分断してしまい、顧客体験が途切れているのが現状です。
たとえば、
- SNSで認知 → LP誘導 → 問い合わせ → 電話商談
- メルマガ → ウェビナー参加 → 展示会フォロー → 成約
といったように、チャネルを“横に並べてつなぐ”設計が、これからの新規集客では不可欠です。
新規集客に使えるオンライン施策
SEO・コンテンツマーケティング:中長期的なリード獲得の資産に
自社サイトへの検索流入を狙うSEOや、課題解決型のコンテンツで信頼を築くコンテンツマーケティングは、“待ちの集客”でありながらも長期的な資産形成に繋がる施策です。
- お役立ち記事・ホワイトペーパー・お客様の声コンテンツなどを活用
- 問い合わせや資料請求といった「顕在層」だけでなく、「潜在層」の育成にも効果的
- Google検索で“指名検索”される状態を目指す

SNS運用・ソーシャル広告:拡散・共感で認知を広げる
SNSは、若年層だけでなくBtoB領域でも重要性が高まっています。
なかでもX(旧Twitter)・Instagram・LinkedInなどは、特定の業界や興味関心での訴求に効果的です。
- 継続的な発信 → 認知拡大・企業理解の促進
- リード広告やフォロワー拡張広告を活用した直接集客
- BtoBなら、個人アカウントを活用した「ソーシャルセリング」も有効
Web広告・LP運用:短期間で反応を得たい場合に有効
- リスティング広告(Google広告、Yahoo広告)
- ディスプレイ広告(GDN/YDN)
- SNS広告(Meta・Instagram・LINEなど)
これらのWeb広告は、“すぐに問い合わせや資料請求を獲得したい”ときの有効手段です。
ただし、ターゲットとLPの訴求がズレると無駄打ちになるリスクもあるため、LP設計・キーワード選定がカギになります。
MAツールによるリードナーチャリング:接触後の育成強化に
獲得した見込み顧客(リード)に対して、メールやコンテンツを用いて自動で継続的な接点を設ける施策です。
- 配信シナリオを組み、顧客の検討フェーズごとに情報を提供
- 開封率・クリック率などの行動データに応じてスコアリング
- Salesforce、HubSpot、BowNowなどのツールが代表例
「獲得したリードを育てて商談化する」という視点で、営業効率化と成約率UPを両立できる仕組みとして活用されています。
新規集客に使えるオフライン施策
展示会・セミナー出展:関心層とリアルでつながる場
- 自社のターゲット層が集まる業界展示会や、課題解決型のセミナーへの出展は、見込み顧客とのリアルな接点づくりに有効です。
- リード情報の獲得だけでなく、その場で温度感の高いリードに直接アプローチできる点が強み。
- フォロー体制をあらかじめ設計しておくことで、商談化率が大きく向上します。
DM・テレアポ・FAXなど:特定業界やターゲットに刺さる手法
- 製造業・建設業・高齢層向けなど、デジタルに接触しづらい層へのアプローチには、紙や電話のチャネルが効果的です。
- FAXDM、郵送DM、テレアポなどは、特に地域密着型の営業でもいまだに活用されています。
- 「オンラインで届かない層」こそ、オフライン施策のチャンスとなります。
既存顧客からの紹介制度(リファラル):質の高いリードが得られる
- 新規顧客を開拓するうえで、既存顧客からの紹介は極めてCV(成約)率が高く、営業コストも抑えられる施策です。
- 紹介インセンティブや紹介キャンペーンを設計し、紹介を仕組み化することで、安定的なリード獲得が可能になります。
- 営業が「売る」のではなく、「信頼を引き継ぐ」構造を作れるのが大きな特徴です。
オフライン施策は、“今すぐ顧客と話したい”ときや、“熱量の高い関係を築く”ときに非常に効果的です。
オンライン施策と併用することで、広く集めて、深くつながる仕組みが実現できます。
集客施策を選ぶ際の判断基準と優先順位
新規集客で成果を出すには、「効果が高そうだから」ではなく、「自社にとって最適かどうか」という視点で施策を選定することが重要です。
施策の選択を誤ると、リソースが分散し、結果としてどれも成果が出ない状態に陥ってしまいます。
ここでは、施策選定の際に見るべき3つの観点と、優先順位のつけ方について解説します。
商材単価・リードタイムに応じて施策を変える
集客手法は、商材の価格帯や検討期間の長さ(リードタイム)によって適正が異なります。
| 商材タイプ | 向いている集客施策 |
| 高単価・検討長期型 | セミナー、コンテンツマーケ、ホワイトペーパー、インサイドセールス |
| 中価格帯 | SNS広告、リスティング、展示会、営業代行など |
| 低価格・即決型 | Web広告(LP誘導)、クーポンDM、LINE公式アカウント活用 |
商材に合わせて「接触回数」「信頼構築の必要性」を考慮することで、施策の方向性が明確になります。
社内リソース(時間・人材・予算)から現実的に逆算する
集客施策には、初期設計・運用・改善サイクルを回す継続性が求められます。
短期的な「やってみた」だけで終わらないよう、以下の視点から施策の選定・設計を行いましょう。
- 運用可能な人員体制・ナレッジはあるか?
- 施策ごとにかかる時間や外注費を捻出できるか?
- 担当者不在でも回る仕組みを用意できるか?
外注を視野に入れるのか、内製で進めるのかも重要な判断材料になります。
自社だけで集客を完結するのが難しい場合は、インサイドセールス代行の活用も有効です。
専門チームにアポ獲得やリード育成を任せることで、営業効率を保ちながら自社はコア業務に集中できます。
特に、営業体制が整っていない段階や、継続的なリード創出を仕組み化したい企業にとっては、実践的な選択肢となります。
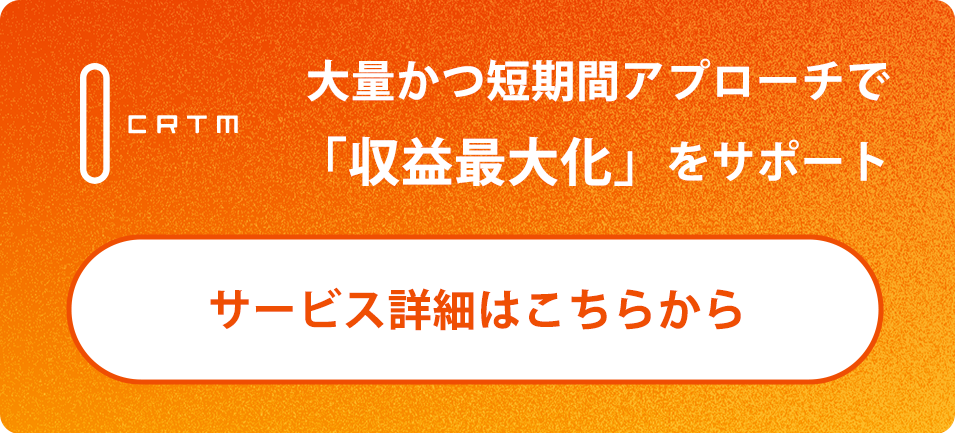
短期施策と中長期施策のバランスをとる
- 短期施策(Web広告、テレアポなど):すぐに効果が出るが、継続コストが高く属人化しやすい
- 中長期施策(SEO、紹介制度、SNS運用など):安定的に効果が出るが、成果が出るまでに時間がかかる
両者を「並行して動かす」ことで、短期と長期の成果をつなぐ仕組みができます。
“今”の集客と、“未来”の資産形成をどう両立させるかという視点で戦略を描くことが大切です。
集客活動にデータを活かす方法とKPI設計

新規集客を“やりっぱなし”で終わらせず、継続的に成果を高めるには「データに基づいた改善」が不可欠です。
しかし多くの企業では、「何を指標にすればいいのか分からない」「数字を見ても改善につながらない」といった悩みを抱えています。
このセクションでは、集客の成果を見える化し、改善サイクルを回すためのデータ活用とKPIの考え方について解説します。
集客チャネルごとの主要KPIと見るべき指標
チャネル別に設定すべきKPI(重要業績評価指標)は異なります。施策の目的に応じて、評価軸を明確にしましょう。
| 施策 | 主なKPI例 |
| Web広告(LP型) | クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、CPA(顧客獲得単価) |
| SEO/コンテンツ | 検索順位、オーガニック流入数、滞在時間、直帰率 |
| SNS運用 | インプレッション数、エンゲージメント率、リンククリック率 |
| MA・メール施策 | 開封率、クリック率、スコアリング反応率 |
| 展示会・テレアポ等 | 獲得リード数、商談化率、成約率 |
KPIは「施策別」だけでなく、最終的な営業成果(商談数・受注数)とつながる指標であることが重要です。
ツールを活用して集客データを可視化する
集客施策の多くは、GoogleアナリティクスやCRM、MAツールと連携することで定量的に把握・改善可能です。
- Googleアナリティクス:流入経路、CV数、離脱ポイントなどの確認
- HubSpot/Salesforce:リード状況や営業との連携ステータスを一元管理
- SFAやMA:検討フェーズごとの温度感分析や配信結果レポートを活用
複数チャネルをまたいで一元管理できる仕組みがあると、部門間での連携・分析の精度も大きく向上します。
改善サイクル(PDCA)を回すためのポイント
施策実行後は、「データ収集 → 仮説立て → 改善策実施 → 検証」というPDCAサイクルを短いスパンで回すことが重要です。
- 成果が出た/出なかった要因を、データとユーザー行動の両面から分析
- 1チャネルごとではなく、「流入~CVまでの導線全体」を見る
- 定点KPIだけでなく、“動き”や“変化”も見て小さな改善を積み重ねる
数字を“見て終わり”にせず、「次にどう動くか?」の判断基準として活用することで、集客の質が格段に上がります。
まとめ|成果を出し続ける新規集客は“仕組み化”がカギ
新規集客で成果を上げるには、施策を単発で終わらせず、
「戦略設計 → 実行 → 検証 → 改善」までを一貫して運用する体制づくりが欠かせません。
オンライン・オフラインを適切に組み合わせ、自社に合った方法で継続的に改善を回すこと。
それこそが、成果を“出し続ける”新規集客の本質です。
新規集客を“仕組み化”したい企業へ!インサイドセールス支援サービス「SABU」のご案内
新規集客は、単発の施策ではなく“仕組みとして継続できる体制づくり”が何より重要です。
特にリソースが限られている中小企業や、これから営業体制を立ち上げたい企業にとっては、
「自社だけでアポ創出・商談化までを回し続ける」ことが難しいのが現実ではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、CRTMが提供するインサイドセールス代行サービス「SABU」。
「SABU」が新規集客の仕組み化に貢献する理由
- リスト作成~アポ獲得~営業プロセス改善まで一気通貫で支援
- “テレアポ型”ではなく“共感ベースのナーチャリング型アプローチ”を実施
- 属人化しない新規開拓体制の構築が可能
特に、BtoB商材や検討期間の長いサービスでは、SABUが得意とする「関係構築型の営業」が強力な成果を生み出します。
詳しくは、「営業リソース不足でも、商談は増やせる!新しい営業活動手法「法人営業支援サービス SABU」で継続的な商談を生み出す」記事をご閲読下さい。
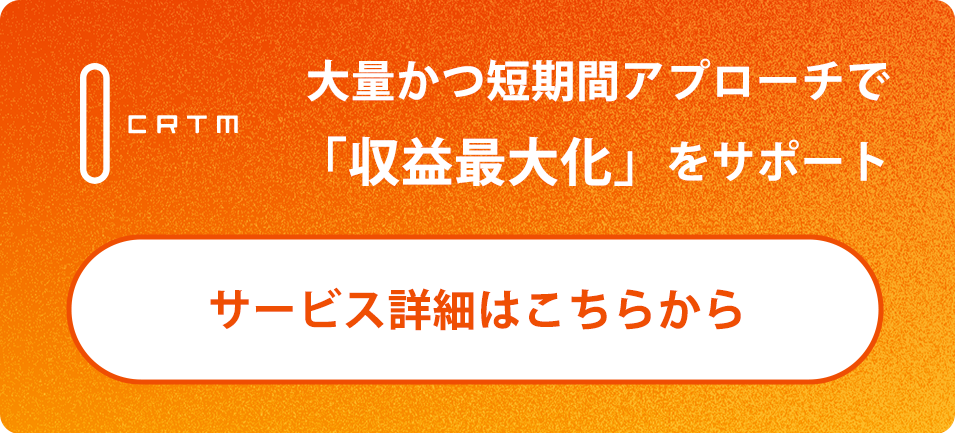


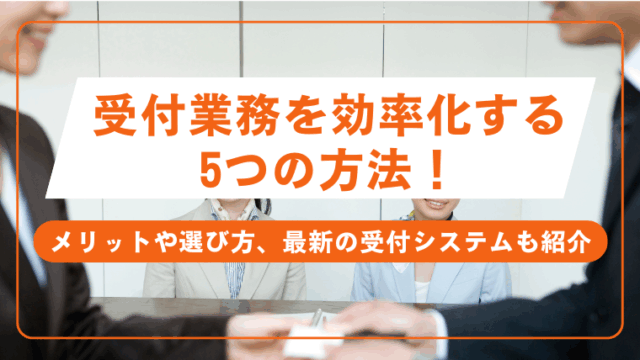
とは?ツールの選び方と導入のポイントを解説-640x360.png)